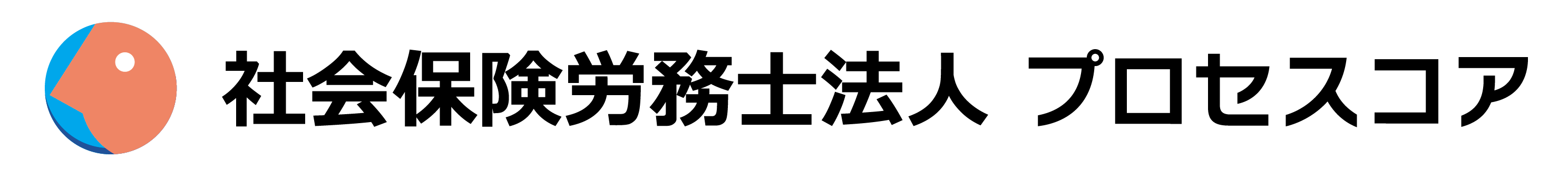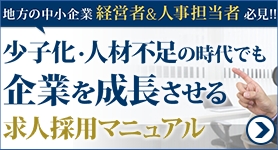気をつけないといけない 人事評価制度4つの落とし穴


目次 [閉じる]
はじめに:なぜ人事評価制度が必要なのか?
中小企業の経営者や人事担当者の皆さま、「人事評価制度は必要か?」と問われたらどうお答えになるでしょうか。
私の個人的な見解では、創業期や社員数が少ないうちは、必ずしも評価制度が必要ではないと考えています。
経営者と社員の距離が近く、日々のコミュニケーションの中で給与や役割の期待が伝わる場合、制度を形式的に整えなくても問題が起こりにくいからです。
しかし、組織が成長し、社員数が増え、勤続年数が長くなると、社員の頭にはこうした疑問が浮かび始めます。
「自分の給与はどう決まっているのだろう?」
「どれだけ頑張れば、どのくらい昇給するのだろう?」
「自分に何が期待されているのだろう?」
これらの疑問に明確に応えられなくなると、社員のモチベーションは徐々に低下し、離職リスクも高まります。加えて、企業が社員に求める行動や能力の期待値が伝わりづらくなります。
そんな時に必要になるのが 「人事評価制度」 です。
ですが、制度を導入さえすれば万事うまくいくわけではありません。
むしろ、よくある 「落とし穴」 に気づかないまま導入・運用してしまい、かえって現場の不満が増してしまうことも...
今回は、特に陥りやすい4つの落とし穴とその対策についてご紹介します。
落とし穴①:評価制度導入の「目的」を見失う
最初の落とし穴は、「制度を導入すること自体が目的化」してしまうことです。
よくあるケースとして、他社が導入しているから、社員に要望されたから、助成金を活用したいから...といった理由で形だけ評価制度を導入し、制度や運用にメリハリがないパターンです。
評価制度の本来の目的は、概ね以下のどれかに該当するかと思います。
- 1.企業が社員に求める行動や能力、成果の期待値を伝える
- 2.給与・賞与決定の透明性を高める
- 3.役職・ランク決定の基準を示す
- 4.社員の成長やモチベーション維持
- 5.企業理念や行動指針の浸透
- 6.部下育成のツールとする
制度導入の前に、経営者自身が「何のために評価制度を作るのか」、「目的の優先順位」を明確にし、それを意識した設計と運用ができているか、チェックしながら設計することが肝要です。
落とし穴②:評価者のスキル不足がモチベーション低下を招く
2つ目の落とし穴は、評価者(上司)が適切に評価面談を行えないことです。
たとえば、評価者が部下の成果や行動をしっかり観察できていなかったり、フィードバックの仕方が一方的だったり感情的なダメ出しだったりすると、社員は「どうせ見られていない」「何を頑張っても変わらない」「期待されていない」と感じ、モチベーションは下がってしまいます。
この問題を防ぐには、評価者研修の実施が欠かせません。
評価項目の意味や評価基準を理解するだけでなく、
- • 日頃から部下の行動を観察する
- • 面談では本人の自己評価・意見・目標も聞く
- • 課題だけでなく、成長したポイントにもしっかり目を向ける
- • 行動改善につながる具体的フィードバックを行う
といった「面談スキル」を磨くことが必要です。
また、評価者の属人化によるヒューマンエラーを防ぐために、評価面談を先輩評価者同席の上で実施したり、事前に査定内容や面談時の伝達内容を確認する評価者会議やロールプレイングを実施することも有効です。
落とし穴③:評価項目の誤解と偏りが意図しない行動を生む
評価項目は、社員にとって「何をすれば評価されるのか」を示す羅針盤です。
しかし、特定の項目ばかりが強調されすぎると、社員がそこにばかり意識を集中し、本来企業が期待している行動とズレてしまうことがあります。
例えば「売上目標達成」だけを重視しすぎると、日頃の勤務態度やルール、チームワークをおろそかにした態度や行動が生まれかねません。
項目や評価項目ウェイトは多角的かつバランス良く設定し、どんな評価要素が加点採点され、減点採点されるのか、評価面談の際には各項目の背景や重要性を丁寧に説明することが大切です。
落とし穴④:評価業務が通常業務を圧迫してしまう
評価制度のもう一つの「現場泣かせポイント」は、評価・面談・査定に時間を取られすぎることです。
特に中小企業では、一人の管理職がプレイングマネージャーとして現場業務と評価業務の両方を抱えている場合が多く、評価シーズンになると業務過多で疲弊しがちです。
この問題を防ぐには、
- • 評価項目・シートをシンプルに設計する
- • 評価時期を長めに設定する。
- (例)評価・面談期間1ヶ月→2ヶ月、評価時期と昇給・賞与査定の実施時期に余裕をもたせる
- • 面談時間をあらかじめスケジューリングする
といった「無理なく回せる運用設計」が求められます。
また、評価採点をするクラウドシステムやGoogleフォームなどを活用して、できるだけ採点入力、集計、記録の保存の手間を減らす方法を考えていきましょう。
人事評価制度の本質は“原資”と“協力”にある
強調しておきたいのは、評価制度が機能することで得たい成果は「社員同士、会社と社員が協力し、生産性を上げて人件費(給与原資)を増やす」ことだと考えます。
社員は、自分の評価や給与だけでなく、
- 売上や利益がどのように増えたら
- どのくらい原資があり
- 自分たちの給与や労働条件にどのように関わってくるのか?
を知ることで、会社と一緒に目標を達成しようという気持ちになります。
経営者が「評価制度=給与決定の仕組み」だけに終始せず、事業の成長と社員の幸せを両輪で考えることが、評価制度を成功させるカギです。
まとめ:制度は会社と社員の未来をつくるツール
人事評価制度は、「導入すれば終わり」ではなく、「導入してからがスタート」です。
- • 目的が曖昧なままでは形骸化
- • 評価者のスキルが伴わないと逆効果
- • 評価項目の設計次第で、社員の行動が望まぬ方向へ
- • 業務負担が過大だと運用停止リスクも
これら4つの落とし穴を避けながら、社員との対話を重ね、制度の改善を続けることが大切です。
評価制度は、社員が安心して働き、成長し、企業とともに未来を描くための「道具」です。
最初から完璧なものをつくることは難しいので、少しずつ改良を重ね、より良い制度を作り上げていきましょう。
活用次第で、会社と社員、双方の未来が大きく変わります。
最後に、評価制度の導入にあたっては、経験がないとどこから取り組めばよいか分からず、時間ばかりが経過して先送りになりがちです。
評価制度の設計を専門にしたコンサルタントや弊所(社会保険労務士事務所)を上手に活用して頂き、制度構築していく方法もありかと思います。
制度設計のサポートを検討される方は、ぜひこちらの人事制度導入支援サービスページをご覧ください。
👉 プロセスコア人事制度導入支援
今回のコラムは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。
〈この記事を書いた人〉
山下 謙治
Kenji Yamashita
社会保険労務士法人 プロセスコア 代表
日越協同組合 監事
社会保険労務士・行政書士・マイケルボルダック認定コーチ
日産鮎川義塾 師範代 九州本校 塾長
社会保険労務士として人事・労務の課題解決を通じて地元熊本を中心に中小企業の経営支援20年のキャリアを持つ。従来の社会保険労務士の業務だけでなく、管理職育成を中心とした教育研修事業や評価制度導入支援を行い、経営者が抱える、組織上の悩みや課題解決の支援を行っている。得意とする業務は、起業から5年目以降の発展期における組織強化・拡大期の採用・教育・評価・処遇といった人事制度づくりの支援。
最近の講演内容
「社員の評価制度と賃金制度のあり方」 肥銀ビジネス教育株式会社主催
「欲しい人材を引き寄せる!求人募集と採用選考の見極め方セミナー」株式会社TKUヒューマン主催

給与計算業務や社会保険手続代行、労使間の法律問題、採用・組織づくりのご相談なら社会保険労務士法人プロセスコアへご相談ください!
社会保険労務士事務所への顧問契約を検討中の方はこちら
社会保険労務士法人プロセスコアの強み・主な提案内容を知りたい方はこちら