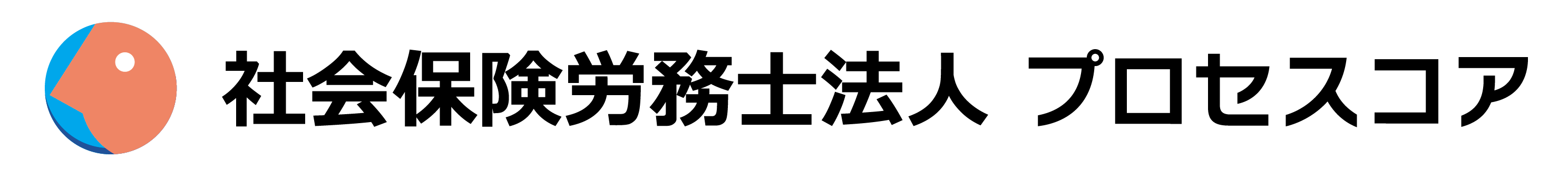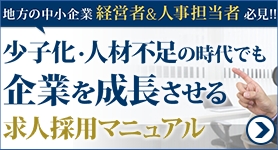生産性向上の鍵は「人事担当者の時間の使い方」

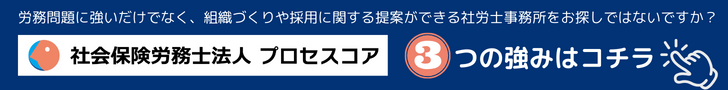
いつもお世話になっております。社会保険労務士法人プロセスコアの山下です。
今回は、経営者や人事担当者の方に向けて、「生産性向上の鍵は人事の時間の使い方」という視点からコラムをお届けします。
近年、企業経営における「人事部門の役割」が急速に変化・拡大しており、その重要性は日々高まっています。
(私がいうと仕事がほしいからそんなこといってるんじゃないの・・?と思われそうですが、実際にお客様からの相談の内容の幅や、真剣に社員の採用や教育の課題相談を受ける機会が4、5年前に比べると数倍に増えている実感があります。)
なぜ今「人事の重要性」が高まっているのでしょうか?
その背景と実践的な対応策について、具体的にお話をしたいと思います。
目次 [閉じる]
なぜ今、人事の時間の使い方が問われているのか?
まずは、昨今の外部環境について整理しましょう。
今、中小企業を取り巻く経営環境はかつてないほどに複雑化しています。
- ・最低賃金の急激な上昇
・原材料費・水道光熱費の高騰
・社会保険料・人件費など固定費の増大
・インフレ傾向による価格転嫁の難しさ
・少子高齢化による人材獲得競争の激化
これらの要因はすべて、企業の「利益確保の難しさ」と「人材確保の難しさ」へと直結しています。
十分にご認識されている方も多いと思いますが、こうした環境下では、単なるコスト削減だけでは限界があり、いかに限られた資源(特に人材)で最大の成果を出すか「生産性の向上」がこれまで以上に強く求められています。
その中心的な担い手は経営者であり、また企業の人事部門だと考えます。
しかし現実には、経営者や人事担当者は「目の前の業務」に追われてしまい、戦略的な人事活動に十分な時間が割けていない現状が多いのではないでしょうか?
では、時間がない中でどのような対策が有効なのでしょう?
代表的な対策と取り組み方法を順を追ってご紹介致します。
1.「仕事の4象限」から考える、人事の優先順位を整理する
時間管理の考え方として、スティーブン・R・コヴィー博士が提唱した「仕事の4象限」があります。
仕事は、以下の4つの領域に分類できます。
- 第1領域 緊急性が高く、重要な仕事
- 第2領域 緊急性は低いが、重要な仕事
- 第3領域 緊急性が高く、重要度は低い仕事
- 第4領域 緊急性も重要度も低い仕事
この中で、生産性向上や組織の未来をつくるカギとなるのは「第2領域」に該当する業務です。
人事における第2領域の代表的な業務を挙げてみましょう。
- ・採用活動の設計(母集団形成、広告媒体や手法、面接、選考フロー見直し)
- ・育成施策の立案と定着(OJT/OFF-JT、教育計画、実施)
- ・目標管理制度の設計と面談運用
- ・社員面談や1on1による信頼関係づくり
- ・自社の行動指針やMISSIONの浸透活動
- ・ヒヤリハットやコンプライアンスの周知、労務リスクの洗い出し
- ・競合企業の人事施策のリサーチと対策立案
これらは緊急性が低いため、後回しにされがちですが、中長期的な組織力・企業価値を高めるうえで、極めて重要な取り組みになってきます。
2.「人事の第2領域」をスケジュールに組み込む
では、実際に人事担当者や経営者は、この第2領域にどう向き合えばよいのでしょうか。
結論から申し上げると、「スケジュールをブロックして、時間を先取りする」ことが鍵になります。
忙しい日常業務の中では、まとまった時間が自然に空くことはありません。
そのため、1年単位、四半期単位、月単位、週単位で計画的に人事戦略の時間を「ブロック」して確保する仕組みが求められます。
たとえば、
- ・毎月第1火曜日は全社目標レビューと人材戦略会議
- ・毎週金曜日午前は1on1と育成振り返り
- ・四半期ごとに「採用・育成・定着戦略」見直し会議や合宿
こうしたスケジュールの「型」をつくることで、後回しにならず、ある程度のスピード感をもった継続的な運用が可能になります。
3.専門家との伴走による仕組みづくりの加速
ただし、社内リソースだけで第2領域の活動を推進するのは簡単ではありません。
- ・優先順位がつけにくい
- ・進め方のノウハウがない
- ・現場との連携が難しい
このような壁に直面した際は、はっきりいって宣伝にはなりますが、、、弊所(社労士)や人事コンサルタントといった外部の専門家の力を借りることはとても有効です。
特に、「壁打ち相手」として、外部からの視点とアドバイスを得ながら、人事制度や育成計画、中長期の経営計画を下にした、人事戦略や計画を見直すことが、着実な成果につながります。
4.AI等のシステムの活用で「作業」を減らす
もう一つ、忘れてはならない視点があります。
それが「業務効率化による時間の創出」です。
近年、ChatGPTなど生成AIの発展により、書類・文案の作成、マニュアル整備、データ分析、確認作業などにかかる時間は、やり方によっては従来の半分以下に短縮できる可能性のある時代になってきました。
例えば、
- ・募集要項や面談記録のひな形作成
- ・勤怠データの文字起こしや集計や分析レポートの作成
- ・研修資料のドラフト作成
こうした事務・作業系の業務はAIやシステムによって「自動化・時短化」し、その分、創造的で人間的な「第2領域」の仕事に集中できる環境をつくることができます。
そのためにはまずAIに代表されるデジタルシステムで今何ができるかを知り、活用していく動きも同時に進めていく必要があります。
まとめ:「人事の時間の質」が未来の企業価値を決める
本コラムを通じてお伝えしたいことは、「人事の時間の使い方」こそが、企業の未来を左右するということです。
(どうしても宣伝ぽくなりますが多くの企業にとって事実だと思います。)
忙しい日々のなかでも、意図的に時間を確保し、育成・定着・採用といった基盤に投資する。
私自身も日々格闘の毎日ですが、強い意思をもって第2領域の仕事時間の予定をブロックして推進していく重要性を日々感じています。
今回のコラム、いかがでしたでしょうか?
第2領域であげた業務のスケジュール、しっかりブロック出来てますでしょうか?
もし、まだな部分がございましたら、ぜひ実行されることをお勧めします。
私たちプロセスコアも、クライアント企業様の第2領域の推進をサポートすべく、サービスを充実していきたいと思います。
最後に弊所の第2領域業務の推進サポートのサービスのご紹介です。
経営者含めた幹部、中堅、一般社員まで一緒に学び、組織力の底上げを図ることができる人材教育研修サービス「人財育成顧問」のご利用がお陰様で増えてきております。

クライアント企業様については、1回のみのお試し受講もご用意しておりますので、ぜひご活用をご検討ください。
今回のコラムは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。
〈この記事を書いた人〉
山下 謙治
Kenji Yamashita
社会保険労務士法人 プロセスコア 代表
日越協同組合 監事
社会保険労務士・行政書士・マイケルボルダック認定コーチ
日産鮎川義塾 師範代 九州本校 塾長
社会保険労務士として人事・労務の課題解決を通じて地元熊本を中心に中小企業の経営支援20年のキャリアを持つ。従来の社会保険労務士の業務だけでなく、管理職育成を中心とした教育研修事業や評価制度導入支援を行い、経営者が抱える、組織上の悩みや課題解決の支援を行っている。得意とする業務は、起業から5年目以降の発展期における組織強化・拡大期の採用・教育・評価・処遇といった人事制度づくりの支援。
最近の講演内容
「社員の評価制度と賃金制度のあり方」 肥銀ビジネス教育株式会社主催
「欲しい人材を引き寄せる!求人募集と採用選考の見極め方セミナー」株式会社TKUヒューマン主催

給与計算業務や社会保険手続代行、労使間の法律問題、採用・組織づくりのご相談なら社会保険労務士法人プロセスコアへご相談ください!
社会保険労務士事務所への顧問契約を検討中の方はこちら
社会保険労務士法人プロセスコアの強み・主な提案内容を知りたい方はこちら