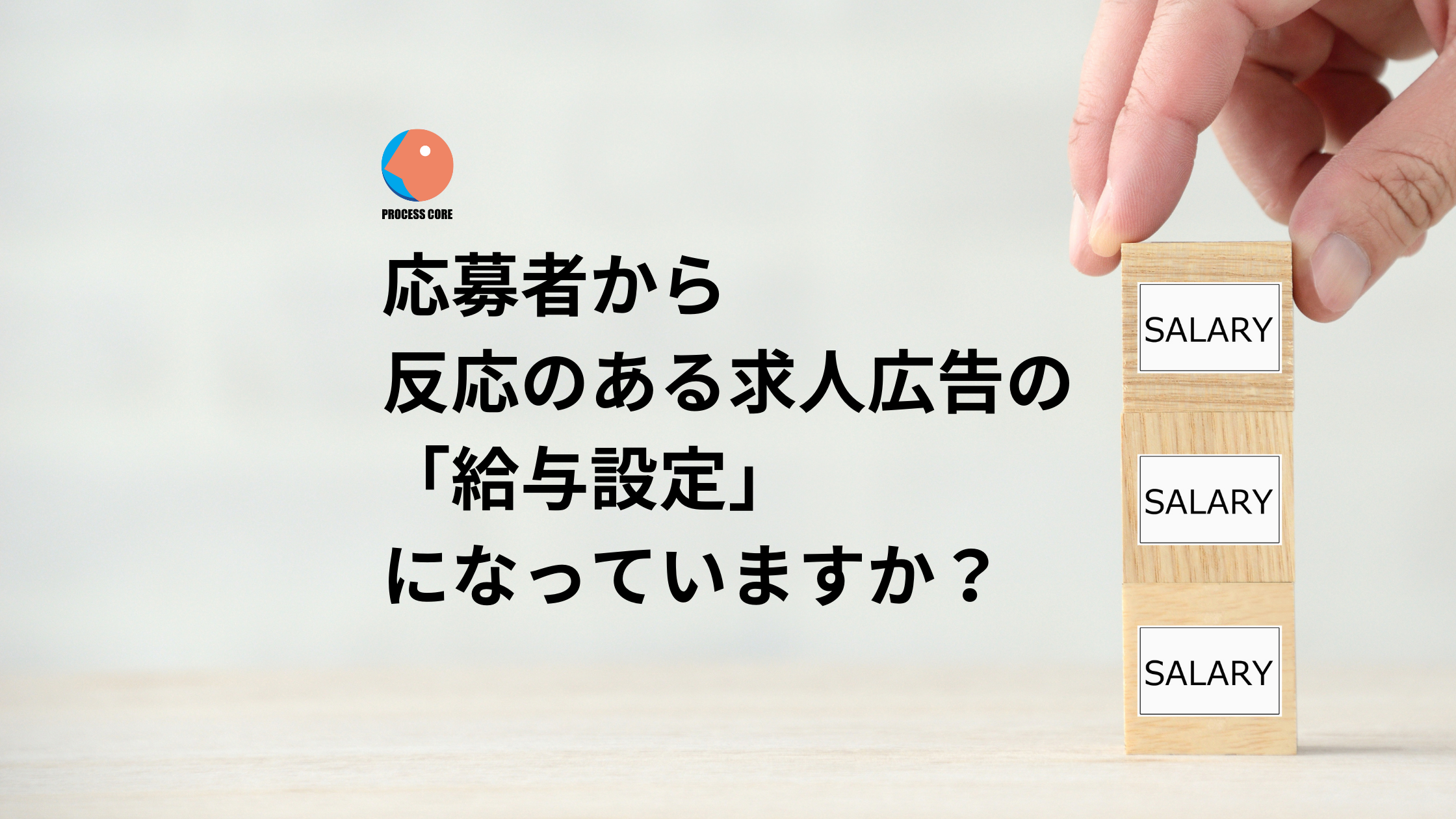
大手就職・転職支援サイトが行う求職者を対象とした仕事選びの基準についてアンケート結果を見ると、「仕事内容」、「勤務地」、「事業内容」と肩を並べて「給与や手当」といった項目は、例年上位3~4位以内に位置づけられています。企業側から見ても、求人活動を優位に進めるためには給与設定(下限・上限設定)はとても重要です。
今回は、求人広告に載せる給与設定について以下のポイントをご紹介します。
ポイント!
募集する求人職種についてIndeedやハローワークのデータを検索して、近隣エリアの同業他社の求人広告の水準を分析して、平均値より1割ほど高め(可能であれば給与の下限額が全体の上位2~3割に入る設定)で求人広告を行うこと
理由は、コロナ禍の状況下で一時的に求職者が増えてはいるものの、少なくとも今後10年は売手市場(求職者優位)が続きます。
競争原理が働く状況下では、よくあるお見合いパーティーや合コンパーティ-と同じで、人気のある人にアプローチが殺到するように、給与設定が高い企業に応募者が集中することになるからです。
よくこのようなお話をすると相談された方から、求人広告の給与設定を上げると、以前入った従業員から「自分が採用された頃よりも高い」といった不満の声が出るのでは?という声を聞きます。
この場合は、既存の従業員の方々に外部環境の変化に対応していかなければいけないことや、企業が成長して待遇をよく出来るようになってきたことなどを説明し、必要に応じて従業員の給与のベースアップを行うなどして理解を得ていく必要があります。
人件費を上げることはコスト的に難しいとお話される方もいらっしゃいますが、その場合は、コスト増に耐えうるビジネスモデルの見直しが必要かもしれません。
また、人に依存しないようなシステム化の推進やビジネスモデルに転換を図ることも選択肢の一つだと思います。
ただ、どの業態でも、一般的に大なり小なり人にしかできない業務は少なからずあります。
特に事業が、人への依存度が高いサービス業である場合、すぐに人材が育つわけではありませんので、一時的にコスト増になったとしても先行投資として実行していく必要があるかもしれません。
躊躇して対応が遅れると、企業の成長スピードが鈍化・停滞する可能性が高くなりますので、どのような方針で進めていくか、早い判断が求められます。
今回のコラムは以上です。
もし、求人広告を出してはいるが反応がない、少ないといった経営者・人事担当者様は、上記の取り組みや課題についてご検討ください。

ワークエンゲージメント…日本語でいうと「働きがい」という言葉が一番近い表現かと思います。
今、企業の生産性を高めるためには従業員・組織のワークエンゲージメントを高める施策を実施する企業が増えてきているようです。今回はワークエンゲージメントの視点から企業の求人活動の取り組みについて触れたいと思います。
ワークエンゲージメントという言葉の定義は文献等によって変わりますが、本文では、「従業員が主体的に会社や仕事に取り組む充実感や就業意欲」を総合的に指す言葉と定義します。
以下の9つがワークエンゲージメントを高める鍵と言われていますが皆様の企業の社員の方々はどのように感じられているでしょうか?
1.職務…職務に対して満足度を感じているか?
2.自己成長…仕事を通じて自分が成長できているか?
3.健康…従業員が仕事の中で過度なストレスや疲労を感じていないか?
4.支援…上司や仕事仲間から職務上または自己成長の支援を受けているか?
5.人間関係…上司や仕事仲間と良好の関係が築けているか?
6.承認…周りの従業員から認められていると感じているか?
7.理念戦略…企業の理念・戦略・事業内容に対して納得・共感しているか?
8.企業の組織風土が従業員にとって良い状態なのか?
9.給与・福利厚生・職場環境といった従業員を取り巻く会社環境に満足しているか?
会社側は1.~9.すべての項目について改善を続ける努力が必要と思いますが、従業員の趣向性や価値観にも大きく左右される項目も多く含まれています。
例えば、1.職務(仕事内容)、2.自己成長、7.企業の理念や戦略、8.組織風土、9.給与・福利厚生といった職場環境
ワークエンゲージメントを高めるには企業努力が必要な一方、従業員個人の価値観に委ねられている部分もあります。採用の視点でこの点を考慮すると、採用後のミスマッチを防ぐために企業側が求人広告や自社の求人サイトに、いかに上記の9つに関する情報を掲載し、発信しているかが重要になります。是非、自社のサイトや求人広告の内容を一度チェックされてみてはいかがでしょうか?
74058806771fdfd65021894dc9868cb4こんにちは、プロセスコアの山下です。
新型コロナウイルスの影響が続いていますね。
ニュースでもこの話題がもちきりなので、巷でも明るい話題や雰囲気になりづらいように思えます。
こういう時ほど、普段の日常生活の中では、周りの人を笑顔にする、
冗談をいって楽しませる、そういった心配りを常に心がけたいものです。
企業経営者や管理職といったリーダーの方であれば尚更で、職場の士気や雰囲気を大きく左右すると思います。
率先して、笑顔や明るい話題を提供していきたいものですね。
では、今回のメールマガジンは、
================
民法改正による、「身元保証書」の上限額記載の必要性
================
について解説をしたいと思います。
本来、今回のテーマはもう少し早いタイミングでお伝えしないといけない情報であったのですが、お伝えするのが遅くなってしまい、申し訳ございません。
対応を行わなければいけない企業様は、従業員採用時に身元保証書を取られている企業様となります。
(身元保証書とは、企業と採用する従業員の保証人の間で取り交わす身元保証契約のことで、従業員がなんらかのトラブルを起こし、企業に損害を与えた場合に、従業員と連帯して身元保証人に賠償を行うことを約束させる効力が発生します。)
変更内容は、
保証人の保護強化の観点から、今年の4月1日以降に採用した従業員から身元保証書に損害賠償の限度を記載していないと身元保証書は効力が無効となります。
今後の企業対応策としては以下の2つが考えられます。
1.「身元保証書の上限額を記載する運用方法に変更する」
2.「身元保証書の制度を廃止する」
では具体的に1.2.それぞれのポイントを解説をします。
1. 「身元保証書の上限額を記載する運用方法に変更する」
については、賠償額をどのように決めるかがポイントになるかと思いますが、上限額は法律では決まっておらず、企業側で自由に設定することが可能です。
しかし、上限額が決まっていないからといって例えば、『1,000万円』と記載したとしてもおそらく、身元保証書にサインをもらうのは難しくなることが想定されます。
逆に上限額が「10万」、「20万」といった少額だと、そもそも身元保証書を取る意味が失われることにもなるので、100~200万円といった具体的な数字でかつ、支払いが可能で現実味のある金額を定めた書式に変更する必要があります。
2.「身元保証書の制度を廃止する」
についてですが、 「何かのときに…」、「念のために…」といった感覚で身元保証書を取っており、形骸化している、また、過去に従業員本人に損害賠償を請求したことはあっても、身元保証人に対しては損害賠償請求を行ったことがないし、今後も損害賠償請求する可能性がほとんどないという企業様については、身元保証書を取るルールを廃止することも選択肢も一つとして検討頂きたいと思います。
本当に身元保証書を取る必要があるのか?
何の為に保証書を取るのか?
目的について改めて再考し、取る必要があれば、書式を変更したもので継続し、必要がなければ、廃止することも一つの方法かと思います。
そういった場合でも、従業員採用時に従業員に何かしらの事情があって連絡が取れなくなった際の緊急連絡先として保証人候補の方の連絡先を登録して頂くことをお勧めします。
以下の書式を参考にご利用頂ければと思います。
・身元保証書(新様式)
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1k_claUXl88Bricg80gV4WYBFU–RXp0u/view?usp=sharing
・緊急時連絡書
↓↓
https://drive.google.com/file/d/186lYlHNrQzKJLyUBkOJgqo_NGTQCrSvs/view?usp=sharing
・関連サイト
法務省リーフレット
「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが 大きく変わります」
↓↓
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、有難うございました。
(最近のメールマガジン配信記事)
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0319)
(2020.3.19配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0319.html
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0311)
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2011-031102.html
■Web会議サービスのご案内です。
(2020.3.11配信)
https://process-core.com/process-core/2020-3011.html
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0305)
(2020.3.5配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0305.html
■新型コロナウイルスへの企業対応策についてのお知らせ(0304)
(2020.3.4配信)
https://process-core.com/process-core/2020-0304.html
おはようございます。
プロセスコアの山下です。
12月も半ばに入ってきましたね。
今年は年末にかけて、お客様から労使トラブルの御相談を例年より多く頂いているように思います。
一般の企業では2.3年に1度起こるか起こらないかといった退職勧奨、懲戒処分、解雇事案について数多くご相談頂き、私を含め事務所スタッフが様々な経験をさせて頂いていると思います。
先日、経営者の方からの依頼で問題のある従業員の方へ退職を勧める話合いに同席させて頂く機会がありました。
そういった場面で改めて思ったことは「言葉」の重要性です。
言葉は使い方によって「凶器」になると言われることがありますが、確かに言い方一つで相手を傷つけたり、猛烈な反発を買うことがあります。
また、高圧的に「力」や「感情」で相手を制圧しようとすると、相手も同じように感情的になって反発を買い、最悪労働紛争にまで発展することがあります。
逆に、どんな人であっても自分を大事に扱ってほしいという承認欲求があることを忘れず接することができれば、自然と言葉・態度に配慮が生まれ、注意や処分、退職勧奨をする際の言葉であっても相手にとって伝わり方はマイルドなものになります。
労使トラブルのご相談を頂くことで誰かに意見したり、注意、指導をする際の自分自身の日頃の態度や言動について改めて考える機会を頂いたように思います。
皆様はいかがでしょうか?
言葉や相手に与える印象一つ一つを大事にしていきたいものですね。
今回のメールマガジンは、来年1月に開催する弊所主催の勉強会のお知らせです。
「企業経営者及び人事担当者の為の組織の仕組みづくり「はじめの一歩」セミナー」と題しまして、
私が労務顧問として17年やってきた中で、定着率を上げ、組織を順調に成長させている企業がどのような「仕組み」を初期段階に構築しているのか?事例や考え方のポイントをお伝えするセミナーです。表面的にはみえづらい企業の組織開発の取組みについて解説していきます。
以下のような悩みをお持ちの経営者及び人事担当者の方に是非受講いただきたいと思います。
○ 良い人材が採用できない、定着しない
○ 社員の成長が遅い、管理職が育たない
○ 社内ルールや業務フローが整備されてなく、無駄な業務時間のロスが多く発生している
○ 経営者を中心とした管理職層に仕事が集中している
○ 会社が求め、期待していることとは違う目標を立てたり、取り組みを行っている
○ 計画を立てても誰も動こうとしない、なかなか進まない
○ 企業全体の現状や目標についての理解度や関心度が低い
上記の一つ一つの項目について自社の組織上の課題があるのか?ないのか?発見して頂けるような企業の事例や考え方をご紹介する勉強会にしたいと考えており
ます。
(主な内容)
・上手に採用活動を進めている企業とそうでない企業の考え方の違いは?
・社内ルールを浸透させる為の仕組みや運用方法
・成長スピードを上げるために必要な「役割」や「目標」、「権限」、「責任」の共通認識
・組織での「位置」を認識させる組織図の必要性
・ケースに応じた評価基準の作り方のポイント
・昇給はどのくらいのペースで進めていけばいい?
・経営戦略と組織の仕組みを連結させる
・管理職の育てるために中長期計画
安定期に入ったベテランの企業の経営者や人事担当者の方におかれましても管理職候補の方の育成や後継者育成にお役立て頂ける内容かと思います。
参加ご検討の程どうぞ宜しくお願い致します。
■ 開催日・時間帯
2020年1/21(火)、1/28(火)のいずれかの受講希望日
14:00~16:00 (受付13:45~ )
※経営者の方で業務の都合上日中の参加がどうしても難しい方については、日時を個別に設定して開催を検討させて頂きます。
(別途費用が発生します。ご了承ください。)
■開催場所
社会保険労務士事務所プロセスコア
会議室〒862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目46-27
REGALIA SUIZENJI 3F
申し込みは以下のフォームからお願いします。
↓↓
https://forms.gle/AkjLpVs6gRKyiqQx6
■参加費
1名あたり5,000円(税込)1事業所2名まで
(通常出張研修で30,000円以上で実施して いる内容です。)
■定員:6名
開催日の7日前までにお申し込みください。 (申し込み先着順)
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、有難うございました。
おはようございます。
プロセスコアの山下です。
女子ゴルフの渋野日向子選手、大活躍ですね! 全英AIGオープン、日本人選手として42年ぶり のメジャー優勝の快挙。ニュースもその明るい話題で持ちきりで見ている方も明るい気持ちになりました。
昨日、その話題についてスタッフと移動中の車の中で話をしていたら、スタッフから「あれだけ (渋野選手が)笑顔だと福も寄ってきますよね!」 という発言を聞き、まったくそのとおりだと 納得してしまいました。
今回の渋野選手の活躍を見て笑顔でいることの大切さを改めて教わったような気がします。
さて、今回のメールマガジンは、来る9月3日火曜日に開催される弊所主催のセミナーのご案内です。
====================
「欲しい人材を引き寄せる!
求人広告と選考時の人材の見極め方セミナー」 のご案内
====================
「求人広告を出しても応募がない!」
「採用選考の精度を高めて自社にあった人材を採用したい!」
そんな求人募集や採用選考に携わる経営者および人事担当者の為のスキルアップセミナーです。
定着率の低下や労使トラブルの未然防止、組織のレベルアップも「採用」の成否が大きく影響していることを顧問先企業様から日頃お受けしている労務問題を通じて年を追うごとに痛切に感じています。
組織の規模にもよると思いますが、 「採用」は中小企業において経営者の方がもっとも力を入れなければいけない仕事の一つだと思います。
今回のセミナーは、
今後、求人活動や採用選考に携わる人材を育てる為の勉強の場としても良い機会かと思います。
また、最近の求人対策の必須ともいえる、求人サイト作りやGoogle仕事検索、Indeed等ネット対策についても事例をもとに解説したいと考えています。
関心のある方は是非ご参加ください。
開催日時:令和元年9月3日
火曜日 14:00~16:30(受付開始13:30~)
セミナー内容:
1部 14:00 欲しい人材を引き寄せる、人材採用時の見極め方
2部 15:15 欲しい人材を引き寄せる、求人募集活動
3部 16:00 弊所からの提案・質疑応答
場所:くまもと県民交流館パレア 会議室3
定員:30名(顧問先企業様優先)
参加費:5,000円/1人
(顧問先企業様は1名あたり3,000円) 1企業2名まで参加可
詳細は、下記の案内チラシをご確認ください。
↓↓
https://drive.google.com/file/d/1MmaD0VONzcgdw83Ip6NofjUZMM75YSNP/view?usp=sharing
お申込方法は、上記案内チラシをダウンロードしてFAXして頂くか
下記の入力フォームからも行うことができます。
↓↓
https://forms.gle/HMkc43Lxid67zPS88
ご参加心よりお待ちしております。
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。
おはようございます。プロセスコアの山下です。
長いGW期間が過ぎ、皆様いかがお過ごしで
しょうか?
お客様から
連休も通常通りお仕事をされていたという声を
お聞きしたり、
連休が長く、かえって仕事が溜まってしまったと
いう声をお聞したりと、(弊所もどちらかというと
後者に当てはまっておりますが、、、^^;)
それぞれ大型連休についての休日数やシフトの
調整について考えられる点が多かったのでは
ないかと思います。
休日が多かった分、平日の残業が多くなって
本業に支障がでるようではいけませんし、
1ヶ月や1年といった長いスパンで見た際に
労働時間が適正な範囲に収まっているのか、
生産性が向上しているのか、検討して
いく必要があると思います。
さて、今回のメールマガジンは、求人対策を
考える上で重要な、若者の働き方に関する意識調査
について触れたいと思います。
======================
今回のトピック
若者の働き方に関する意識調査から分かること
======================
「求人を出しても応募がこない」
「応募はあるけど、応募者数が少なくて良い人が
こない、選べない」
そんな悩みをお客様から聞かない日はないぐらいの
状況下になってきているように感じます。
この状況下を少子高齢化だからという外的環境の
理由にして何も行動に移さないと企業の成長は
おろか、淘汰される厳しい環境下に入ってきて
いると思います。
では、求人対策として何をすれば良いのか?
国内での採用を考えていく上でまず重要なことは、
相手を知ること…今の若者の考え方を知ることから
始まると思います。
そこで今回のメールマガジンは、
日本最大級の求人情報サイト、エン・ジャパンが
運営する総合求人/転職支援サービス「エン転職」が
2017年9月29日に行った、「仕事の価値観」について
のアンケート調査結果について触れたいと思います。
(調査は、エン転職を利用する20代の男女を対象とし、
2287人から回答を得たものです。)
アンケート結果が掲載されているサイトは下記から
閲覧できます。↓↓
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1710/10/news050.html
20代の若者が「仕事に求めること」の調査結果に
よると
上位順にいうと
1位が「プライベートを大切に働けること」(59%)
2位が「人間関係の良い職場環境で働けること」(55%)
3位が「自分らしい生活ができること」((40%)
であり、下の順位は、
6位「より多くのお金をもらうこと」(36%)
7位「人や社会に役に立つこと」(34%)
8位「専門スキルや知識が身につくこと」(33%)
となっていました。
このデータを見ると、
企業側の視点では、給与を上げれば人が集まると
考えがちですが、それだけでは足りず、また、
必ずしも給与が高い企業でないと人が集まらない
わけではないともいえると思います。
(あまり同業他社と比較して低いと問題
ですが、同業他社の中でできれば上位3.4割に入る
くらいを目安にして良いと思います。)
また、「仕事をする上でやりがいを感じること」に
ついての調査結果は、
上位順にいうと、
1位「スキルアップや自分の成長を実感すること」53%
2位「興味のある分野の仕事をすること」40%
3位「自分の提供した仕事に対して顧客が満足すること」39%
とあり、下の順位に
6位「新しいことに挑戦すること」
7位「責任ある仕事を任されること」
「尊敬できる上司や先輩と仕事をすること」
8位「チームで仕事をすること」
となっており、個人の成長や自分の適性に
あった仕事を通じて人の役に立ちたいという
欲求が強いことが伺えます。
(私の個人的な感想ですが、20代の人達と
交流する中で感じることは、40代以降では
当たり前のように思われがちな、
社会人としての「〇〇すべき」とか、
「○○しなければ」といった、いわゆる社会常識
を固定概念のように若者に当てはめようと
すると非常にコミュニケーションギャップ
というかズレを感じてしまうような気が
しています。)
このデータ結果を素直に読み解くと、
自社の求人サイトや求人広告媒体に掲載する情報に
ついて、以下の情報が記載していく必要が
あるでしょう。
「仕事だけでなく、個人のプライベートの時間も大切に
している企業であることが分かるものになっているか?」
「人間関係の良い職場環境であることが伺い知れる
ものになっているか?」
また、
「新人から経験を積むことでどのようなキャリアを
積めるのか?
キャリアプランをイメージさせるものがあるか?」
「職種に応じてどのような適性を持つ人が
向いているか? 」
「仕事を通じてどんなやりがいを 感じることが
できるのか?」
「自分のした仕事が誰にどんなふうに喜んで
もらえるのか?」
(※注意書きとして
あくまで統計データですので、すべての人に上記の
ような傾向が当てはまるわけではなく、
自社の企業に必要な人材はどんな人材か?という点も
併せて検討していく必要があると考えます。)
皆様の求人サイトや求人情報の内容は
いかがですか?
ぜひ一度チェックしてみて頂ければと
思います。
(アンケート結果が掲載されているサイトは下記から
閲覧できます。↓↓)
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1710/10/news050.html
今回のメールマガジンは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。
おはようございます。
社会保険労務士事務所プロセスコアの木下です。
気持ちのいい秋風が吹き渡るころとなりました。
朝夕は少し肌寒いくらいですが、季節の変わり目は
何かと体調を崩しやすい時期ですので、
皆様、体調管理にはどうぞご留意下さい。
さて、今回のメールマガジンでは、労働条件の
通知方法についての法改正情報をご紹介します。
先日、厚生労働省が、労働条件の通知方法を、
書面だけでなく電子メール等でも可能にすると
報じられました。労働基準法に基づく省令を
改正し、2019年4月から適用する方針です。
労働条件の通知書は、労働契約を交わす際
(従業員を採用する際)に使用者が労働者に
提示することが労働基準法に規定されています。
提示方法については「事項が明らかとなる書面」
とされており、違反すれば罰則もあります。
今回の改正の具体的な変更点としては、
労働者が希望した場合には、
①ファクシミリの送信
②電子メール等の送信(労働者が電子メール等
の記録を出力することにより書面を作成するこ
とができるものに限る。)
により明示することが可能、というものです。
希望した労働者だけに限った措置とし、
労働者が電子メール等での受け取りを拒む場合には、
これまで通り書面で交付する必要があります。
労働者が希望したとき、および、出力(印刷)
できるとき、というポイントはありますが、
トラブル防止のためにも明示の方法の選択肢
として検討してもよいかも知れません。
○●○最近の動き(Topics)━━━━●○●
1. 就活ルール 現在の大学2年生について
は従来ルールを維持(10月16日)
2. 介護事業所の認証制度が始まる(10月15日)
3. 外国人労働者の永住が可能に(10月11日)
「就活ルール」撤廃へ 経団連(10月10日)
4. 電子メール等による労働条件通知書交付
が可能に(10月8日)
5. 休み方改革で中小企業に補助(10月5日)
6. 65歳以上雇用へ法改正(10月5日)
7. 新在留資格 大幅拡大へ(9月29日)
8. 女性就業率初めて7割超(9月28日)
9. 外国人就労 企業向け指導・相談体制
強化へ(9月27日)
10. 地方の中小企業を対象に最低賃金上げで
助成金増額へ(9月17日)
11. 安倍首相「70歳超の年金受給選択」3年
で制度改正を表明(9月16日)
○●○━━━━━━━━━━━━━━●○●
1. 就活ルール 現在の大学2年生について
は従来ルールを維持(10月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15日、政府は2021年春入社の学生(現在大学
2年生)の就職活動時期の新ルールに関して、
現行日程(3年生の3月に説明会解禁、4年生
6月に面接解禁)を維持することで大筋一致
した。現在大学1年生以降のルールについて
の検討は来年以降になるとみられる。9日に
経団連が、2021年春入社組から「就活ルール」
(採用指針)を撤廃することを決定していた。
2. 介護事業所の認証制度が始まる(10月15日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、介護事業所の人手不足対策と
して、研修や休暇制度など働きやすさに焦点
を当てた認証制度を始める。「明確な給与・昇
級体系の導入」「休暇取得や育児・介護との両
立支援」などの項目を設定して介護事業所を
評価・認証する。今年度中にガイドラインを策
定し、来年度以降、全国の都道府県での実施を
目指す。
3. 外国人労働者の永住が可能に(10月11日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人労働者の受入れ拡大のため、政府は新
たに2種類の在留資格「特定技能1号、2号」
(仮称)を設け、来年4月の導入を目指す。
技能実習生(在留期間最長5年)が日本語と
技能の試験の両方に合格すれば「特定技能1
号」の資格を得られる。在留期間は最長5年
で、家族の帯同は認められない。さらに難しい
試験に合格すれば「特定技能2号」の資格を
得られ、家族の帯同や永住も可能となる。
4. 「就活ルール」撤廃へ 経団連(10月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経団連は、2021年春入社組から「就活ルール」
(採用指針)を撤廃することを決定した。これ
を受け、政府は採用日程などを協議する関係
省庁連絡会議を設けることを発表。早ければ
10月中にも結論が出る。また、内閣府と文部
科学省の調査から、就活ルールを守っていな
い企業が62.4%(前年比3%増)あったこと
がわかった。
5. 電子メール等による労働条件通知書交付
が可能に(10月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働者への労働条件通知書について、従来の
書面による交付に代えて電子メールやファク
スなどによる交付が可能になる。労働基準法
施行規則改正により来年4月から適用。電子
メール等による受取りを希望した労働者に限
られ、印刷してそのまま書面化できるものに
限られる。労働者が電子メール等での受取り
を希望しない場合は、これまでどおり書面で
交付しなければならない。
6. 休み方改革で中小企業に補助(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は中小企業の休み方改革を後押し
するため、ボランティアや病気療養などを目
的とした特別休暇制度を導入する中小企業を
支援する。就業規則に特別休暇の規定を盛り
込み、実際に残業時間が月平均で5時間減っ
た場合に最大で100万円を助成する。2019年
4月から実施する。
7. 65歳以上雇用へ法改正(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、現在65歳までの雇用確保措置が義務
となっている継続雇用年齢を、65歳以上に引
き上げる法改正を検討する。どの程度、企業に
強制力がある制度にするかは今後詰める。政
府は70歳を超えてから公的年金の受給を開始
できる制度改正も検討しており、年金と雇用
の両面から高齢者が活躍できる仕組みを作る
方針だ。
8. 新在留資格 大幅拡大へ(9月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人労働者の新たな在留資格として14業種
が候補に挙がっており、政府は、その中から十
数業種を対象とする方針であることが明らか
になった。当初は、5業種としていたが対象を
拡大する。来年4月の導入に向け、秋の臨時国
会に出入国管理法改正案等を提出する予定。
候補業種は、農業/介護/飲食料品製造業/
建設/造船・舶用工業/宿泊/外食/漁業/
ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製
造/電子・電気機器関連産業/自動車整備/
航空。
9. 女性就業率初めて7割超(9月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総務省の労働力調査で15~64歳の女性の就業
率が前年同月より2.1ポイント高い70.0%と
なり、比較可能な1968年以来初めて7割とな
った。男性の就業率は83.9%で、男女合わせ
た就業率は77.0%と過去最高だった。
10. 外国人就労 企業向け指導・相談体制
強化へ(9月27日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、来年4月から在留資格が広が
る(農業や介護、建設などの業種で、一定の技
能や日本語能力を持つ外国人に最長5年の在
留資格を認める)ことに伴い、新たな在留資格
を得た外国人を受け入れる企業向けの指導・
相談体制を強化する。企業を巡回する指導員
や職業相談員約170人を全国の拠点に配置す
るなどし、外国人が働きやすい環境整備を目
指す。
11. 地方の中小企業を対象に最低賃金上げで
助成金増額へ(9月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚労省は、企業が最低賃金を引き上げた場合
に労働者数に応じて助成する「業務改善助成
金」の見直しを行う。現在は、最低賃金を30
円以上引き上げた場合、すべての都道府県で
一律に50~100万円を助成しているが、2019
年度に最低賃金が800円未満の地方企業につ
いては、最大170万円に増やす。最低賃金が
低い地域の底上げがねらい。
12. 安倍首相「70歳超の年金受給選択」3年
で制度改正を表明(9月16日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安倍首相が、14日の自民党総裁選の討論会で、
年金の受給開始年齢が70歳を超える選択もで
きる制度改正について、「3年で断行したい」
と表明した。厚労省も同日の社会保障審議会
の部会で選択できる年齢幅の拡大を論点の1
つに提示。2020年にも制度改正の法案を国会
に提出する方針。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
おはようございます。
プロセスコアの山下です。
サッカーワールドカップいよいよ開催
しましたね。
初戦、日本チームは、コロンビアに大金星、
決勝トーナメント進出の可能性がぐっと
上がってきました。
24日第2戦のセネガル戦も楽しみです。(^^)
今回のメールマガジンは、次の2つのテーマのご紹介です。
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○
1. 新卒採用等の企業PRにつながるブライト企業認定の募集について
2. 企業組織内の「ルール」や「考え方」を浸透させる上での参考書籍紹介
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●
では、1つ目のテーマについて
ご存知の方も多いと思いますが、一定の労働条件や環境整備が
整っているとして熊本県が認定した企業に対して「ブライト企業」
という認定を与える制度のご紹介です。
(応募期間締切り期限が迫っておりますのでご紹介させて
頂きます。)
新聞、雑誌、認定企業を紹介する専用ガイドブック、県庁
ホームページへの掲載 されますので、求職者や学校からの
認知度を向上させたり、
ブライト企業のみを集めた合同PRイベントに参加できたり、
学校進路指導教員と認定企業との情報交換に参加することが
でき、実際に認定を取られた企業様からも、
新卒者採用に関して、認定を取られていない企業よりも一歩
リードしたかたちで求人採用活動ができるメリットがあるとの
声をお聞きしています。
応募要件は下記のとおりです。
1.正社員の採用に関する権限がある事業所を熊本県内に
有する法人、個人事業主又は企業組合で、雇用保険及び
社会保険への加入義務があり、就業規則を整備していること
2.以下の全てに該当すること
・過去3年間における正社員の年間平均離職率が、業種平均の
離職率よりも低いこと。
(弊所で、社員の方々の入退社のデータ管理をさせて頂いている
企業様については、上記基準をクリアしているか確認させて
頂きます。)
・今後(3年以内)に1人以上の正社員の採用予定があること。
・直近3年間において、学生、生徒等のインターシップや
職場体験の受入等の実績があること。
・ 直近2期の決算の営業利益が黒字であること、
又は、直近の売上が前期より増加していること。
※ 平成28年熊本地震以降の決算において、
地震が直接の原因となって生じた決算営業利益の赤字、
売上の減少がある場合は、当該決算期の前2期を対象とする。
・過去3年の間に法人等の都合による解雇を行っていない。
・ 過去3年の間に労働行政に係る司法処分を受けていない。
・ 現在、違法な時間外労働や賃金不払(残業代含む)を
行っていない。
・ 労働保険、社会保険及び県税の滞納がない。
・ その他、公序良俗に反する行為及び過去に
重大なコンプライアンス違反を行っていない、または
それらに関連して係争中ではない。ただし、処分が終了し、
社会的信頼を得られた企業は除く。
3.労働者の過半数を代表する者から応募及び
応募書に記載の内容に対する同意を得ていること
(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、
労働組合の代表者からの同意でもよい)。
ブライト企業募集案内や募集要項は下記ページから
ダウンロードできます。
↓↓
https://furusato-shigotonet.jp/site_bright_companies/newsdetail/mid_id:77/id:415
現在認定を受けられている企業一覧は下記ページから確認
できます。
↓↓
https://furusato-shigotonet.jp/site_bright_companies/brightcom_list/all:1
募集期間は、6/4~7/13までとなっております。
是非、条件を満たす可能性のある企業様や今後認定を
受けること検討されている企業様は、詳細を確認される
ことをお勧めします。
次に、
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●
企業組織内の「ルール」や「考え方」を浸透させる上での
参考書籍を紹介させて頂きます。
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●
組織が大きくなってくると、企業経営者の考えや理念に沿った
姿勢や考え方が浸透しづらくなってきます。
企業内のルール違反の行動が見られることが多くなったり・・
経営者が求める仕事の水準に満たない人が増えてきたり・・
企業の問題や状況を他人事のように考える人が増えてきたりと
そもそもこのような問題は何故起こるでしょうか?
ご紹介する書籍には、以下のようなことが要因の1つだと
書かれてあります。
↓↓
人は「独自のルール」を持っています。これまでの
人生経験の中で、異なる環境に身を置いてきた個人が、
「独自の常識」、「判断基準」、独自の「普通はこうする」
を持っています。
よって組織内において具体的に規定された「ルール」や
「マニュアル」、「基準」といったものがないと、
人それぞれの「常識」として認識しているとおりの
判断や行動、態度を取るので
「なんでそんなことするの?」といったやりとりが
頻繁に起こなわれ、組織内でのルールの答え合わせに
膨大な時間を取られることになると・・・
では、企業組織内で、具体的にどのようなことについて
「ルール」や「マニュアル」、「基準」が必要なのか?
どのような点に企業経営者や管理職の方は気をつければ、
社員の方々に企業組織内の「共通のルール」や「価値観」
「常識」を持ってもらうことができるのか?その解決の
ヒントが見つかる書籍です。
職場内での、個々人の常識のズレや答え合わせによる
コミュニケーションロスを減らし、
生産性をもっと高めたいという考えのある方にお勧めです。
是非、ご一読ください。
関心のある方は、是非下記リンクをクリックしてご確認ください。
(※注 決してアマゾン贔屓をしているわけではなく、書籍の
イメージ・概要紹介です。)
「伸びる会社はこれをやらない」著書 安藤 広大
↓↓
今回のコラムをお読み頂き、ありがとうございました。
おはようございます。
プロセスコアの山下です。
いよいよ12月、今年も
残りわずかとなってきました。
忘年会等の飲み会で街中に
出られる方も多いのではないかと思います。
私も、週末は忘年会に参加させて頂いて街に出たのですが、大変人
通りが多く、活気があって嬉しくなりました。(震災後の街中と
ついつい比較してしまいます、、、)
いつも人が多く、元気な街であってほしいものですね。
さて、今回は、企業の採用活動に関する教材のご案内です。
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●
1.教材「ほしい人材を引き寄せる!中小
企業経営者の為の求人募集・採用選考
キットのご案内
○●○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○●
求人募集・採用選考に悩む中小企業経営者
の為の教材を作りました!
「求人広告を出しても応募者が集まらない」
「定着率が上がらない」
「採用選考に自信がない」
そんな悩みを持つ経営者・人事担当者の為の
教材を作りました。
少子化による人材不足の求人募集市場に
おいて「なんとなく求人広告を出してきた」
「なんとなく面接の際の雰囲気や印象、勘で
採用を決定してきた」といった場当たり的な
採用が明らかに通用しなくなってきています。
しかし、厳しい市場の中にあっても上手に
採用活動を進められている企業は存在します。
中長期的な視点を持った採用戦略と、求人活動
から採用選考まで、成功に導くための仕組みや
導線をつくり、運用しているからです。
教材は、DVD動画と、便利な書式集を収録したCDと
教本のセットで、実際に採用活動に成功されている
企業の事例を交え、採用選考基準作り⇒求人募集⇒
採用選考⇒雇用契約のポイントを解説しています。
採用活動にあたる人材育成の教本としても十分に活用頂けると思います。
本教材で得られる主なノウハウ
・採用を成功している企業とそうでない企業の
採用についての考え方の違いや戦略を学ぶことが
できます。
・曖昧になりがちな採用選考基準を確立すること
ができます。
・採用選考時に確認が漏れがちな、定着率を
見極めるポイントや労使トラブルを未然に
防ぐポイントが分かります。
・採用選考の際に応募者を見極める為の明日
からすぐに使える採用面接や筆記テストを
入手できます。
・求職者の応募を増やす効果的なハローワーク
の求人票、民間求人広告、求人サイト等広告
媒体の作り方が学習できます。
購入、ご検討の程宜しくお願い致します。
(下記から申込用紙をダウンロードして
faxにてお申込みください。)
↓↓
顧問先業様に限り、割引価格17,800円(税込み)
にて販売致します。
(下記から申込用紙をダウンロードしてfaxにてお申込みください。)
(なお、教材の販売はwebページ上でも行っております。)
↓↓