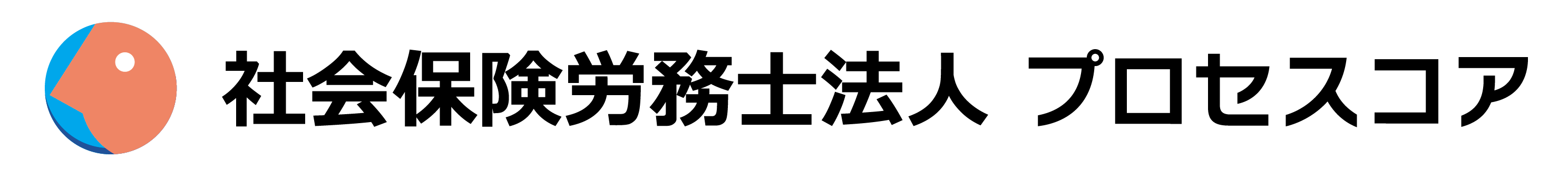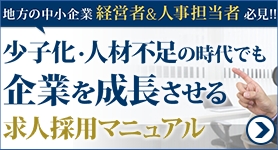問題社員対応 ― 顛末書兼誓約書の有効活用 ―


企業の人事担当者や経営者が最も頭を悩ませる問題の一つが、いわゆる「問題社員」への対応です。
指導を繰り返しても同じようなトラブルやルール違反を繰り返し、周囲のモチベーションを下げたり、組織風土を悪化させたりする社員の存在は、職場全体の生産性に大きな影響を与えます。
今回は問題社員の行動を抑制するうえで、顛末書兼誓約書の有効活用の方法についてまとめました。
是非ご一読ください。
目次 [閉じる]
1.注意しても改善しない問題社員の実情
例えば、業務報告書の未提出、遅刻の常態化、上司の指示に対する反抗的な態度、あるいは顧客対応における重大なミスなど。
多くの経営者や人事担当者は、注意・指導・面談・文書での指摘など段階的な対応を取っているにも関わらず、問題行動がなかなか改善されないという現実に直面しています。
特に、「反省の色を見せながらも同じことを繰り返す」「形式的には謝るが行動が変わらない」といったケースでは、指導の効果に疑問を持たざるを得ません。
2.退職勧奨や解雇への反発リスク
こうした問題行動が続いた場合、企業としては「退職勧奨」や「懲戒解雇」などの処分を検討することになります。
しかし、いざ退職を勧めたり、懲戒処分を行おうとすると、本人が強く反発し、「理不尽だ」「不当解雇だ」「パワハラだ」と主張して、労働基準監督署や弁護士を通じて訴えてくるケースも珍しくありません。
「何度も注意したのに改善されなかった」という企業側の主張が、記録不足や対応の不備によって認められない事態は、裁判事例でも繰り返し見られています。
3.「顛末書兼誓約書」の有効活用を提案
このような状況を防ぐために、弊所が関与先企業様にお勧めしているのが「顛末書兼誓約書」の活用です。
これは、問題行動があった事実を社員本人の認識のもとで文書化し、その上で再発防止の誓約を記載する書面です。
口頭での指導ではその場限りになってしまうことが多く、記録にも残りづらいため、トラブルが発生したタイミングで顛末書兼誓約書を提出させることが重要です。
4. 「顛末書兼誓約書」の内容例
以下は、その文書の一例です。
私は、◯年◯月から◯年◯月まで、業務の日報を◯回提出せず、◯回注意を受けたが改善することが出来ませんでした。
今後は改善することをお約束します。
もし同様の行為があったら会社が定めるいかなる懲戒処分を受けたとしても異議申し立てしません。
このように、自らの非を明文化し、今後の約束と処分受容を記載することで、社員に対する抑止効果を高め、指導の実効性を確保することができます。
5.「顛末書兼誓約書」の効果
この書類には以下の4つの効果が期待できます。
1. 問題行為の抑制を強く促すことができる
社員自身が「次に問題を起こせば処分される」という認識を持つことで、軽率な行動への抑制が働きます。
口頭での注意よりも、文書に署名することで責任の重みを感じさせることができます。
2.会社が問題行為を重く受け止めていることを伝えられる
単なる注意ではなく、誓約書を交わすという行為を通じて、会社としての厳しい姿勢を明確に伝えることができます。
これは周囲の社員に対するメッセージにもなり、組織全体の規律維持にもつながります。
3.改善の最後のチャンスを与えることになる
サッカーに例えるなら、これはイエローカードです。
「次はレッドカードかもしれない」と社員に意識させることで、自主的な行動改善を期待できます。
また、文書により「約束したのに守れなかった」という事実が生まれ、社員自身も処分を「仕方ない」と納得しやすくなります。
4.懲戒処分の法的裏付けになる
誓約書は、問題行為とその改善指導の履歴、さらに今後の対応に関する合意内容を記した「証拠」となります。
懲戒処分に対するトラブルや訴訟に備えるうえで、法的根拠のひとつとなり、企業側のリスクを軽減します。
まとめ
問題社員への対応は、感情的な衝突や法的トラブルに発展しやすく、企業にとって大きなリスクとなり得ます。
しかし、顛末書兼誓約書を効果的に活用することで、本人に強く改善を促しつつ、トラブルの未然防止、再発防止、そして万一の際の証拠確保と、多面的な効果を得ることが可能です。
「問題行為が起きてから慌てて対応する」のではなく、「事前に記録を積み重ねておく」ことで、組織の秩序と信頼を守ることができます。
問題社員への警告方法の一つとして、ぜひこの仕組みを活用してみてはいかがでしょうか。
今回のコラムは以上です。
お読み頂き、ありがとうございました。
〈この記事を書いた人〉
山下 謙治
Kenji Yamashita
社会保険労務士法人 プロセスコア 代表
日越協同組合 監事
社会保険労務士・行政書士・マイケルボルダック認定コーチ
日産鮎川義塾 師範代 九州本校 塾長
社会保険労務士として人事・労務の課題解決を通じて地元熊本を中心に中小企業の経営支援20年のキャリアを持つ。従来の社会保険労務士の業務だけでなく、管理職育成を中心とした教育研修事業や評価制度導入支援を行い、経営者が抱える、組織上の悩みや課題解決の支援を行っている。得意とする業務は、起業から5年目以降の発展期における組織強化・拡大期の採用・教育・評価・処遇といった人事制度づくりの支援。
最近の講演内容
「社員の評価制度と賃金制度のあり方」 肥銀ビジネス教育株式会社主催
「欲しい人材を引き寄せる!求人募集と採用選考の見極め方セミナー」株式会社TKUヒューマン主催

給与計算業務や社会保険手続代行、労使間の法律問題、採用・組織づくりのご相談なら社会保険労務士法人プロセスコアへご相談ください!
社会保険労務士事務所への顧問契約を検討中の方はこちら
社会保険労務士法人プロセスコアの強み・主な提案内容を知りたい方はこちら