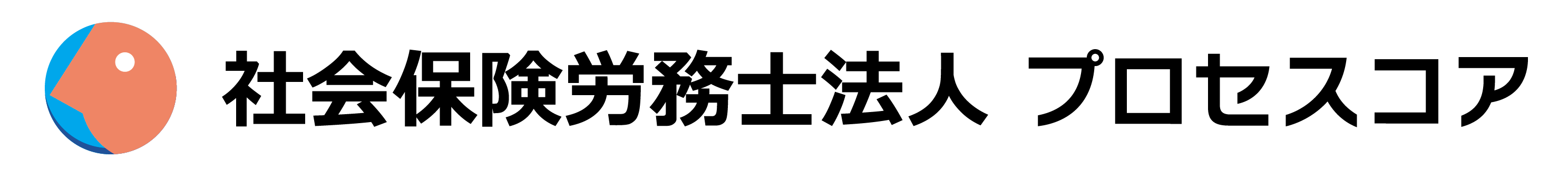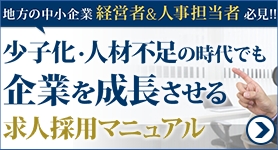どうやって賞与原資を決める?
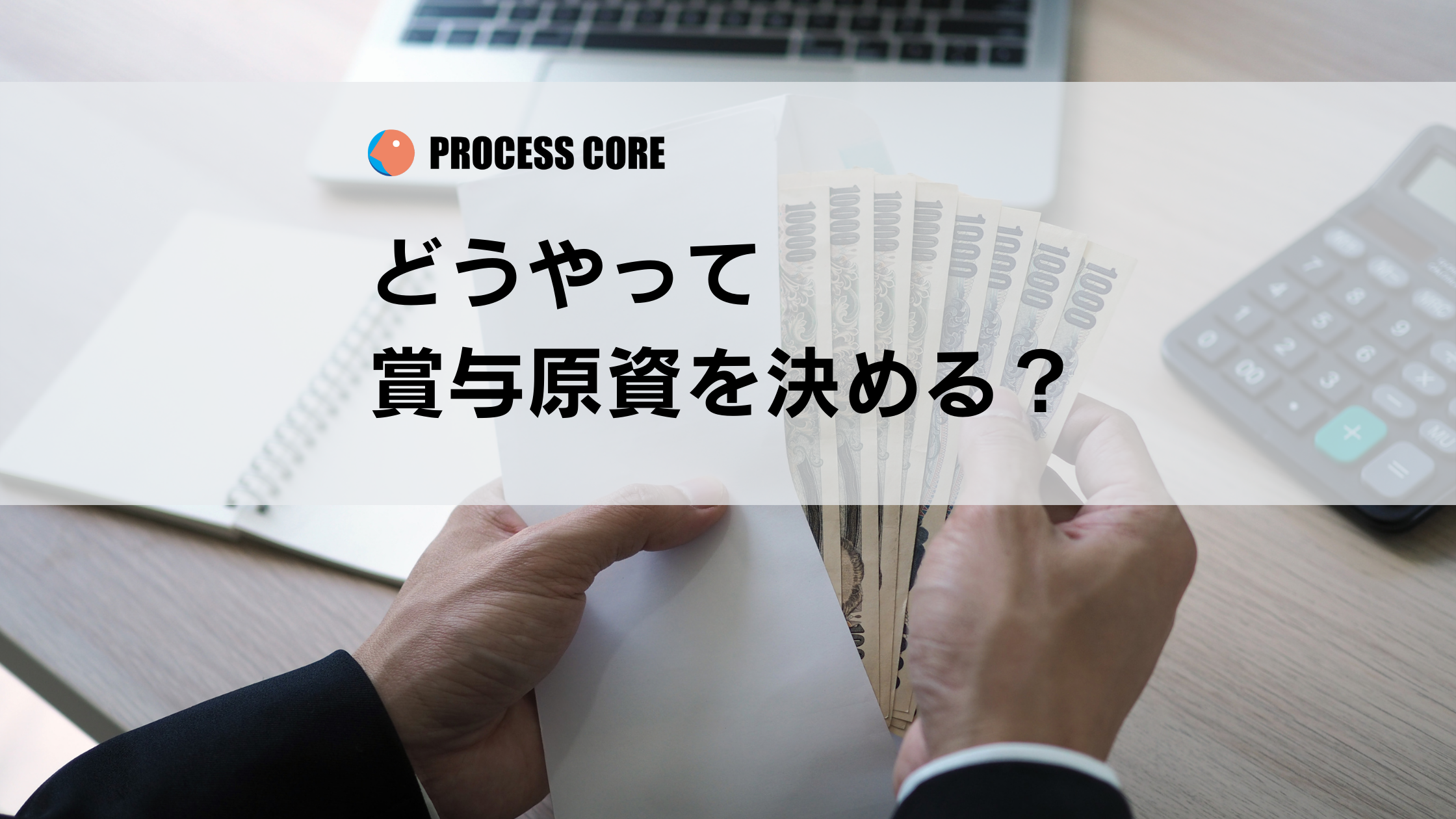
いつもお世話になっております。
プロセスコアの山下です。
年末に近づき、「賞与の原資をどう決めるのか?」企業経営者や人事担当者の方が検討される時期が近づいてきていると思います。
今回のコラムは「賞与原資の決め方」について解説します。
今までは、社員に毎年、月例の給与の1.5ヶ月から2ヶ月程度は、夏と冬にそれぞれ支給すると決めており、特に支払いに問題はなかったが、コロナ禍の状況で業績が安定せず原資を割ってしまって、どのくらいの原資が良いか改めて検討されている企業様もいらっしゃると思います。
そこで、今回は一般的な賞与原資の決定方法を2つご紹介したいと思います。
1つめは、付加価値ベースとして考える方法です。
付加価値(粗利益)をベースとして考える方法
賞与原資 = 付加価値(粗利益)× 労働分配率(%)-(月例賃金 ×12+法定福利費)
一般的に、労働分配率はオーナーの役員報酬も入れますが、賞与原資決定の際にはオーナーの役員報酬は除きます。
ですから「社員労働分配率」という言い方が適切です。
労働分配率により総人件費を算出し、その総人件費から月例賃金分を控除した額を賞与原資とします。
労働分配率は業種業態や経営者の考え方によってもかなり差がありますので、過去数年分の社員労働分配率を実際に計算して、中長期的な企業の業績など考慮しつつ、適正額を決定することがお勧めです
中小企業においては、一般的に労働分配率が33%以内であればとても優秀だと言われています。
2つめは、経常利益(営業利益)ベースの考え方です。
経常利益(営業利益)をベースとして考える方法
「賞与支給前経常利益」の一定割合を賞与原資とする
たとえば、利益の3分の1を賞与原資とします。
これは利益の3分の1は社員に、3分の1は税金等の支払いに、残りの3分の1は内部留保にという考え方に基づきます。
しかし、この考え方に基づくと大半の企業の賞与原資が過小になります。
高収益企業にしかあてはまらない決め方といえます。
上記2つの賞与原資の決め方のいずれにしろ、人事の視点から考えると、以下の2つのポイントを考慮しつつ、決定して頂きたいと思います。
- 1. 過去の支給額との増減の程度
大幅な増減は、来年以降への過度の期待やモチベーションのダウンに繋がる危険性があるので、運用上注意が必要です。 - 2. 一人当たりの粗利益額や伸び率
一人当たりの粗利益額が業界の適正水準になかったり、伸び率が低かった場合、昇給原資を確保することができず、結局賞与原資を削ることになっていきます。
賞与原資の決定は、社員のモチベーションや士気にもかかわる部分ですので、過去の推移と今後の展開を予測しつつ、慎重に決定していきたいものですね。
今回のメールマガジンは以上です。お読み頂き、ありがとうございました。
〈この記事を書いた人〉
山下 謙治
Kenji Yamashita
社会保険労務士法人 プロセスコア 代表
日越協同組合 監事
社会保険労務士・行政書士・マイケルボルダック認定コーチ
日産鮎川義塾 師範代 九州本校 塾長
社会保険労務士として人事・労務の課題解決を通じて地元熊本を中心に中小企業の経営支援20年のキャリアを持つ。従来の社会保険労務士の業務だけでなく、管理職育成を中心とした教育研修事業や評価制度導入支援を行い、経営者が抱える、組織上の悩みや課題解決の支援を行っている。得意とする業務は、起業から5年目以降の発展期における組織強化・拡大期の採用・教育・評価・処遇といった人事制度づくりの支援。
最近の講演内容
「社員の評価制度と賃金制度のあり方」 肥銀ビジネス教育株式会社主催
「欲しい人材を引き寄せる!求人募集と採用選考の見極め方セミナー」株式会社TKUヒューマン主催

給与計算業務や社会保険手続代行、労使間の法律問題、採用・組織づくりのご相談なら社会保険労務士法人プロセスコアへご相談ください!
社会保険労務士事務所への顧問契約を検討中の方はこちら
社会保険労務士法人プロセスコアの強み・主な提案内容を知りたい方はこちら